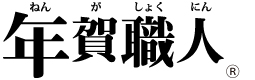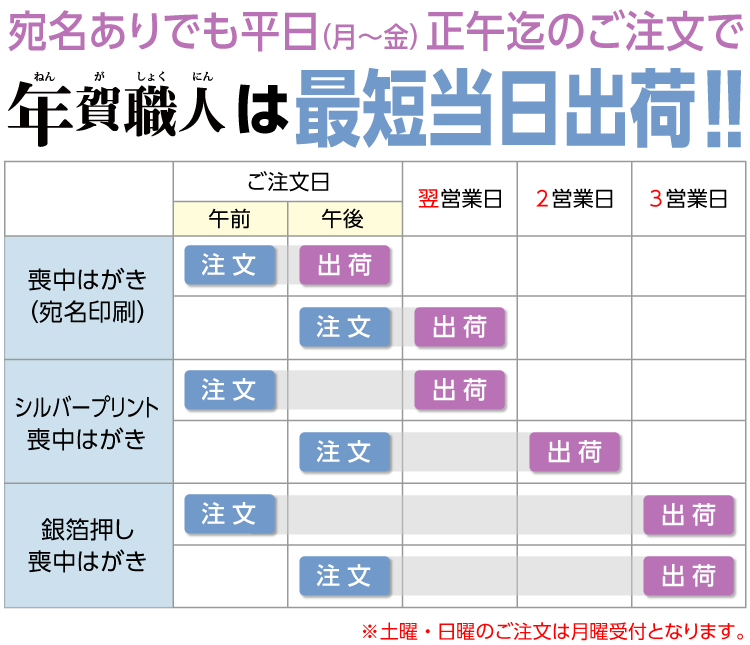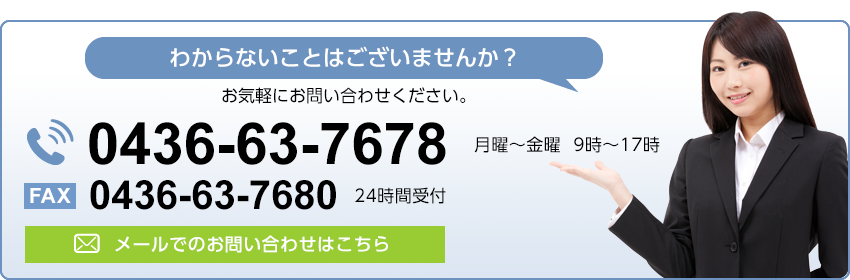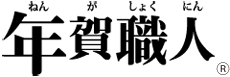寒中見舞い
 寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の習慣の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いである。
寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の習慣の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いである。
現在では、豪雪地帯・寒冷地での相手を気遣う手紙等を指す。また年賀状の返答や喪中のため年賀状が出せない場合の代用にも使う。1989年には前年に昭和天皇の病状悪化(同年1月7日崩御)による「自粛ムード」で年賀状の差し出しが手控えられたため、官製の寒中見舞いはがきが発売された。
また、節分などの行事の参加依頼など、季節の行事への参加依頼なども行われる。
喪中見舞い
 近年浸透しつつある新習慣「喪中お見舞い」。
近年浸透しつつある新習慣「喪中お見舞い」。
「喪中はがき」を受け取った際、従来までは松の内を過ぎてから「寒中お見舞い」でお返事することが習慣でしたがなるべく早めにお悔やみの気持ちを伝えたい…そんな思いから「喪中お見舞い」をお送りする方が増えているようです。
「喪中お見舞い」を送る時期は決まっていませんが、「喪中はがき」はおおよそ12月半ば頃までに届くので、なるべく年内にお届けしたほうがよいでしょう。
| 喪中はがきとは? | 喪中の困りごと | 喪中はがきの文例サンプル |
| 喪中はがきの種類 | 喪中はがきを送る前に | 喪中はがきの用紙について |
| 寒中見舞い・喪中見舞い |